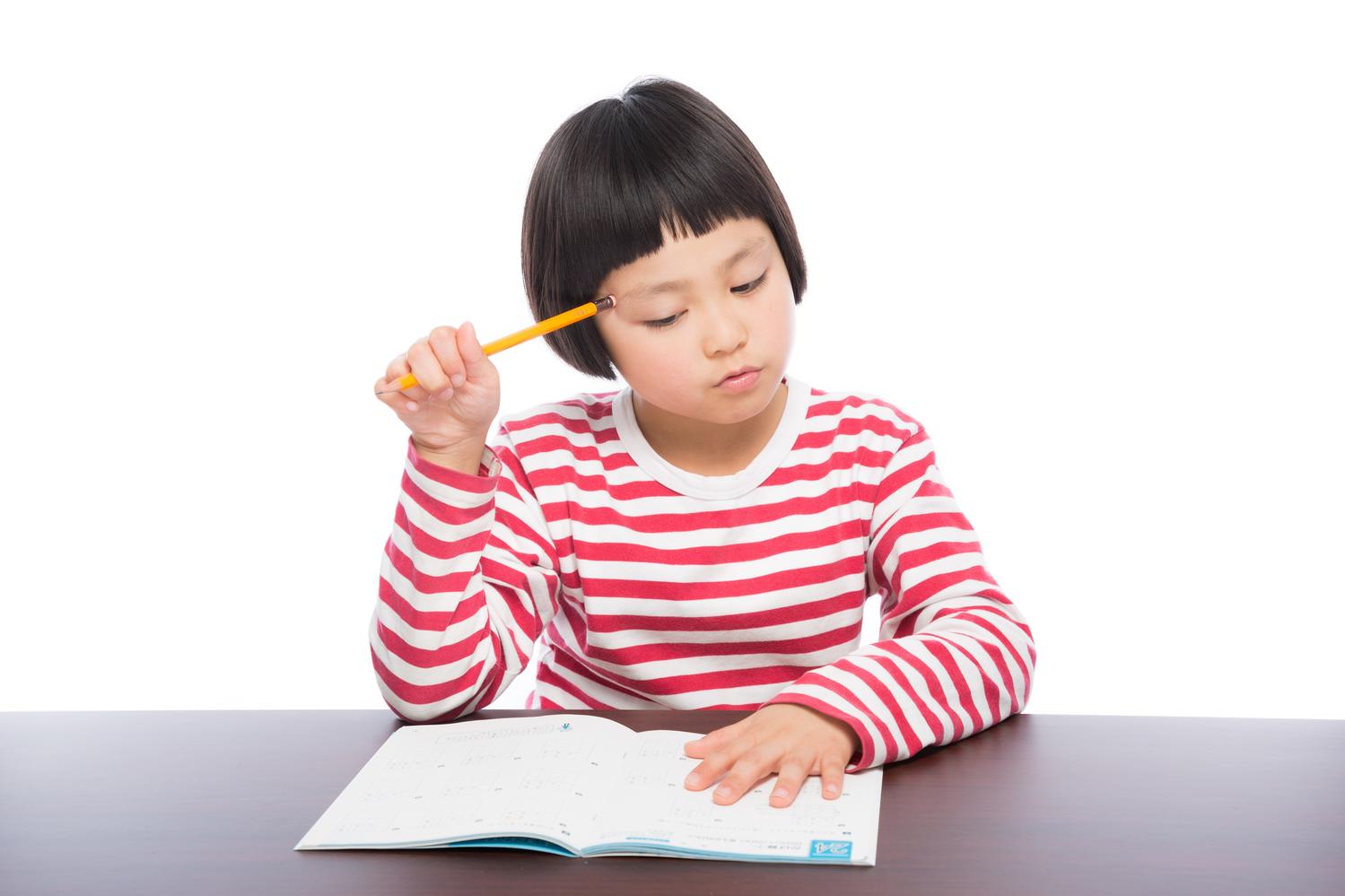
教育行政は学校を休むことを問題にしています。
その考え方自体が間違っています。
「不登校=悪いこと」
「不登校の子ども=悪い子ども」
という考え方こそが問題なのです。
子どもたちは学校を休めないことに苦しみ、親御さんも子どもが学校に行っていないことに罪悪感を感じています。
学校のありかたを含めたすべての子どもを主体とした制度でなければ、全く意味がありません。
この法案では、営利目的の事業所の参入による「第二の学校」を作るだけに終わってしまいます。
すでに、「不登校ビジネス」で高額な相談料を設定している業者やフリースクールも現れています。
フリースクールの中には、補助金で賄っているところもありますので、行政の顔色を見ながらの運営になっているところもあります。
そもそも今の学校制度に無理が生じているのですから、そんな学校に行かなくたっていいのです。
学校に行かせることが目的ではなく、すべての子どもたちに教育の場を保証するのが国の義務なのですから、そのような制度を作っていかなければなりません。
言い訳ばかりの教育行政、時間がない忙しいで片づけている学校現場、それに不満を持っている保護者達。
このような状況や関係を修復することが必要です。
口先だけいいことを言って中身がありません。
個人の努力だけでは限界に来ています。
そのためにもみんなが連帯して、子ども主体の教育制度に変えていかなければなりません。
そのためにまず必要なことは、子どもの思いを聴くこと、保護者の願いを受け止めることなのですが、この段階までいっていないのが現実です。
まずは、そのような場の設定から始める必要があります。
その一方で、教育現場の多忙の改善も求められます。
そのためには、必要のない切れる仕事をバッサリ切り捨てることです。
みんなで取り組めば、できないことではありません。









