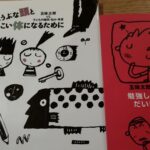2016年度から施行される「障害者差別解消法」によって、公立学校には障害がある子どもたちへの「合理的配慮」の提供が義務付けられます。
しかし、現在でも教員は多忙で疲れ切っているというのも事実で、これ以上個々の教員の負担が増えるようなことになっては、今以上に対応は厳しくなります。
なので、現実問題として保護者の協力は不可欠だと思いますが、それでは親は働きに出ることができなくなり、生活への影響が出てきます。
「合理的配慮」を実施するために教員や保護者の負担が増えることになるのは本末転倒です。
また、これは来年4月以降に施行されるのですが、現時点で学校の人事を含めたハード・ソフト両面での準備がどれだけ進んでいるのかが疑問です。
実情では4月以降に少しずつ整えていくという形になるのではないかという気がしています。
ですが、「障害者差別解消法」は今までになかった画期的な法律であることは確かだと思います。
法の「解釈」や「合理的配慮の範疇」についてもいろいろな問題が生じることも予想されます。
「合理的配慮」に実施にあたっては、教員や保護者の個人の努力に期待するのではなく、学校の人的配置や個々の子どもへの環境整備のための予算要求など自治体や地教委に対して要求していくことが必要になってきます。
それらの要求・要望が出せるようになったという意味では、「障害者差別解消法」を前向きに考えることがいいいと思います。
小中学校で障害児の保護者付き添い、「合理的配慮」で論議も
http://benesse.jp/blog/20151126/p1.html
「障害者差別解消法」を前向きに考える
投稿日:
執筆者:azbooks