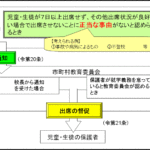今では大人よりも子どもの方がスマホやタブレットに詳しいです。
家庭や友達の間でのやりとりもツールを使って行うのが当たり前になっています。
中高生の9割、スマホ使って勉強「YouTubeで問題の解き方見る」
しかし、日本は学校外・学校内とも、ICTの利用度スコアの平均が最も低いというデータがあります。
教育のICT化が、世界で最も遅れているのが日本です。
デジタル機器やネットでの通信、FacebookやツイッターなどのSNS、言葉は聞いたことはあるけれど、よく分からない。よくわからないから使えない、危ない。
「それって、よく分からない、危険なんじゃないの」止まりの教員も少なくないのではないでしょうか。
ネットやデジタル機器について一番知らないのが、教員なのかもしれません。
今の時代に一番追いついていけていないのが教員なのかもしれません。
子どもたちはIT機器を使い慣れているにも関わらず、教育現場での活用がされていないことが大きな要因です。
教育現場への導入が進んでいない理由には予算面や教員のICT活用スキルの問題などいろいろありますが、一番ネックになっているのは、「スマホやタブレットの学校への持ち込み禁止」という「前例がないからできない」という言い訳です。
学習中にスマホやタブレットを使うことができれば、かなり多くの子どもたちが積極的な学習ができます。
学校へのスマホやタブレットの持ち込みによって、新たに指導方法を考えたり機器の管理が大変になるなど負担が増えると考えている教員も多いですが、その逆です。
子どもたちの学習形態が変わると同時に、教員の学習スタイルも便利で楽になります。
学習形態というと大袈裟ですが、教科書やノートや鉛筆の代わりに端末を使うだけでも学習スタイルは変わります。
今では学級通信やプリントなど、学校からの配布物もほとんどPCで作成したデジタルものになっていますので、いちいち紙に印刷しなくても、各家庭や各端末に即座に送ることも可能です。
自分の苦手な部分をツールで補ったり、友だちや教員との情報伝達手段に使ったりするなど、活用範囲は広いです。
学校予算でICTの導入を行うのはすぐにとはいきませんが、「個人の端末を教室で使ってもいい」ということになれば、すぐにでも授業中に活用することが可能です。
ICTのハード面での導入には時間も必要ですが、学校が「端末の持ち込みを認める」という考え方、教員の「ハート」を変えることはすぐにでもできることです。
教育のICT化を進めるという文科省の方針は出されていますが、その実現を待っていては何も進みません。
情報化社会を生き抜く力を持った人材を育成するためにも、教員の負担を軽減するためにも、児童生徒の学校への端末の持ち込みを認めるべきです。
日本では教育現場だけがICT化から取り残されている
子どもの方がタブレットの使い方を知っているから教員が知らなくてもいい
教員の負担を軽減するためにも教育のICT化を進めることが必要
投稿日:
執筆者:azbooks