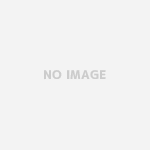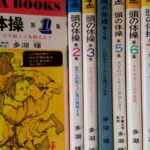「光と同じ速さで、光線の中を走ったらどうなるんだろう?」
この発想がアインシュタインの偉業の一つ、相対性理論を生み出すきっかけになりました。
ここで、アインシュタインの立場になってみましょう。
まだ相対性理論がない時代に、あなたがアインシュタインと同じことをふと思ったとしたら、あなたはそれをどうするでしょう。
子供じみた、役に立たない空想だと、すぐに忘れてしまうのではないでしょうか。
天才と凡人の差は、発想力の差ではなく、自分の発想を大事にできるかどうか。
凡人は、常識にとらわれて、自由な発想にふたをする癖が付いてしまっている。
そのふたを取り払うためにおすすめしたいのが、「ひとりブレインストーミング」。
「ひとりブレインストーミング」なら、誰かに批判されるかもしれないという恐れもなく、自由に考えることができます。
どんなアイディアでも一度紙に書きだしながら、ブレインストーミングを行ってみてください。
馬鹿みたいな考えだと思っても、決して打ち消してはいけません。