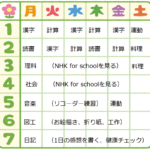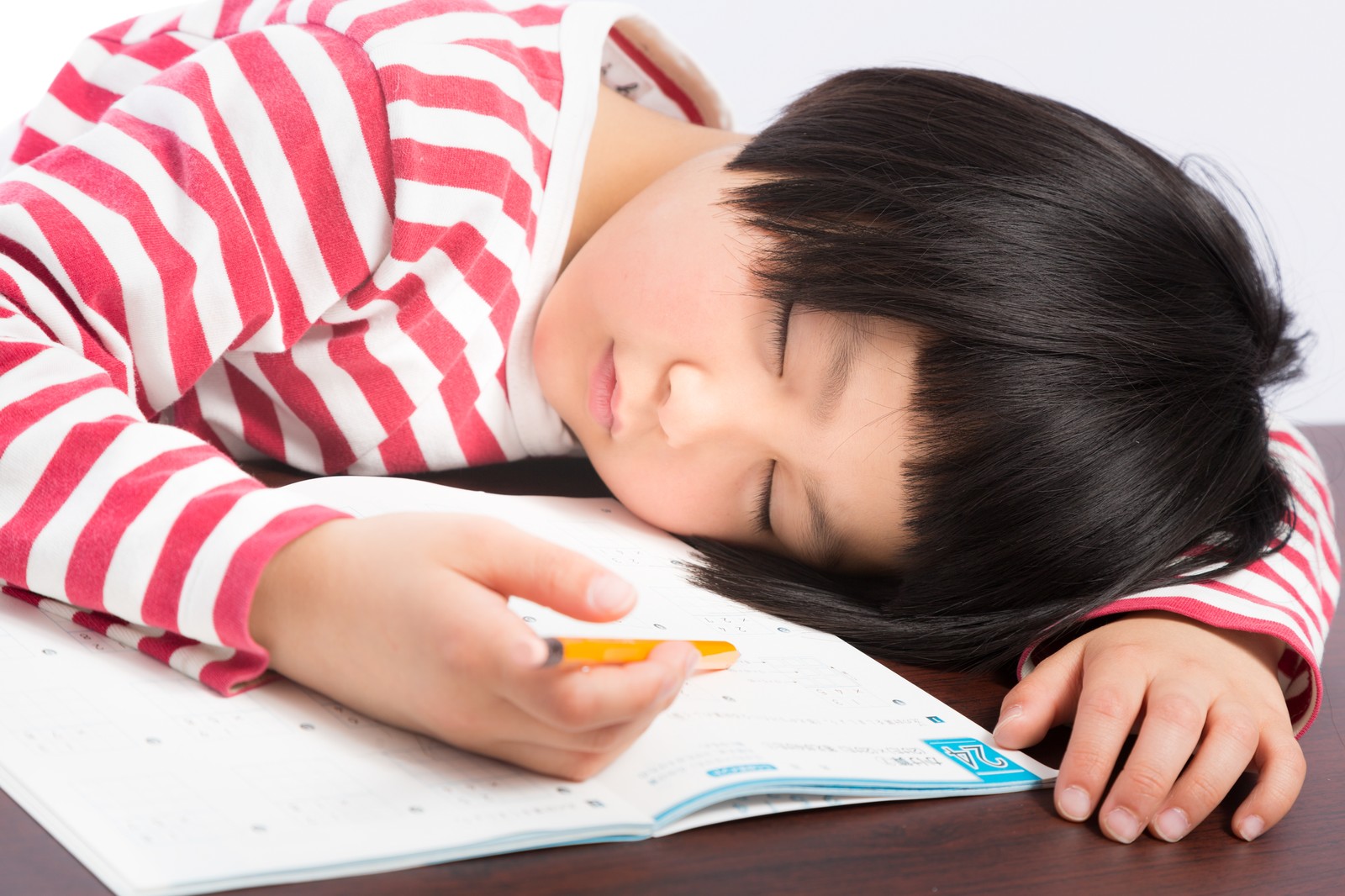
学校の初期対応と親の不安が不登校を長引かせるといいましたが、学校に復帰させることにこだわればこだわるほど、子どもを追い詰めることになります。
私の経験上、親や学校、その他周囲の大人たちが学校に復帰させることにこだわればこだわるほど子どもを追い詰めます。そして、状況を悪化させます。
なぜなら、子どもは「学校に行かなければいけない」ということを誰よりも分かっているのに、それでも行けないから毎日が不安でなりません。
それを誰にも理解してもらえない場合は、自分の殻に閉じこもって絶望の時間を過ごしています。
また、学校の対応が子どもの状態や時期、タイミングによっていい方向に出る場合とそうでない場合があります。
実際に行き渋りの行動が見られた時に、学校側(担任)の対応が必ずしも正解とは限らない場合があります。
学校としては学校復帰にこだわっていますし、不登校の人数を極力減らすことが正しいと信じて疑いません。
教育委員会への「いい報告」も仕事のひとつなので、数字を減らしたいというのが本音です。
学校の先生の立場からすると、「なぜ学校に来たくないのか?」という理由、原因を探ります。
それはそれで一理ありますし、間違いではありません。
ただし、無理に詮索しても子どもが本音を言うかどうかはまた別問題です。
無理に原因や理由を聞き出そうとしても、子どもが本音を話すかどうかはわかりませんし、教師の決めつけで質問を投げかけても問題は解決しません。
子どもは親や教員がどのような返事を期待しているか知っていますので、大人の都合に合わせた答え方をする子もいます。
「本当のことをいっても信じてもらえない」、「親や教員にはよく見られたい」という意識が働き、話をしても聞いてくれない、分かってくれないので話しても無駄だと思っているからです。
教師の決め付けで問題を悪化させる危険性があるため、理由や原因を知るには、ありとあらゆる可能性を考えないといけません。
小学生であればまだ幼いので自分の悩みを整理して相手に話すことも難しく、中学生・高校生は思春期(反抗期)でなかなか本音を大人には話しづらいこともあります。
思春期になると、自分自身のことや周りのことが客観的に観ることができるようになるため、気をつかいすぎて話し辛いこともあります。
そこで、周囲にいる大人が勝手に決めつけず、また本当の理由がどこにあるのか、自身の子どものころの経験を元にしてありとあらゆる可能性を考えるべきです。
また、学校の対応と親の対応では利害が食い違うこともあります。
学校側の対応と親の対応とではとるべき内容が大きく違ってきます。
学校側は何がなんでも学校に登校させるのが正義であり、それが本当の不登校対応だと信じて疑いません。
「親にとってどうか、学校にとって正解は何か」ではなく、「その子どもにとって本当に適切なことは何か」という視点でないと、話し合いは平行線です。
学校側は「親の対応や教育が悪い」、親は親で「学校側は子どものことを真剣に考えていない」となり、対立を深めるだけになってしまいます。
そこで、きちんと双方が話し合いをして、互いを理解し合うことが重要になります。
「今の子どもにとって、本当に大切なことは何か?」という共通の目的に向かって、共にできることをしていくことが大切です。
私は、「無理して学校に行かせることはない」という考えです。
例え義務教育であろうと、学校に行っていなくとも社会で通用する人間になっている例はたくさんあります。
それらを「特別」と称して認めようとしないのは、ちょっと無理があると思っています。
学校復帰を目指す子どももいれば、もう学校には行かず、他の場所で頑張ると決める子どももいますから、その決断を尊重してあげるべきだというのが私の考えです。
親が「今日どうするの、行くの行かないの?」と選択や決断を迫ったり、早く学校に行かせたいという思いから「こうしたほうが良いんじゃないか、ああしたら…」というアドバイスも言いたくなりますが、子ども「行きたくない」思いとのギャップが広がるので逆効果です。
学校復帰するかどうか、どのタイミングでどう行動するかどうかは自分に決めさせてあげて欲しいと思っています。
「本人が何を望んでいるか、どういう方向性で考えているか」を尊重して、親や学校が協力しながら対応の方向性を決めていくが解決は早いと思います。
これが子どもへの対応の「基礎基本」です。
親も教員もこれが出来ていません。
親や教員が学校復帰を迫ったり、早く学校に行かせたいという思いから「こうしたほうが良いんじゃないか、ああしたら…」というアドバイスも言いたくなりますが、子どもの「学校に行きたくない」思いとのギャップが広がるので逆効果です。
逆効果というのは「学校に行かなくなる」のではなく、子どもが親や教員に対して「心を塞いでしまう」という意味です。
基礎基本の第一「学校に行く行かないで子どもを評価しない」ことが最も重要なことです。
ただし、不登校の原因が勉強にあるのであればすぐに対応すべきです。
不登校のときは学校復帰だけを目的としない
投稿日:2015年12月1日 更新日:
執筆者:azbooks