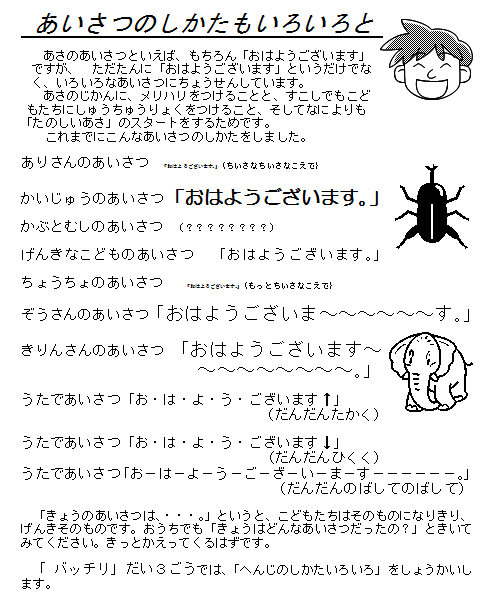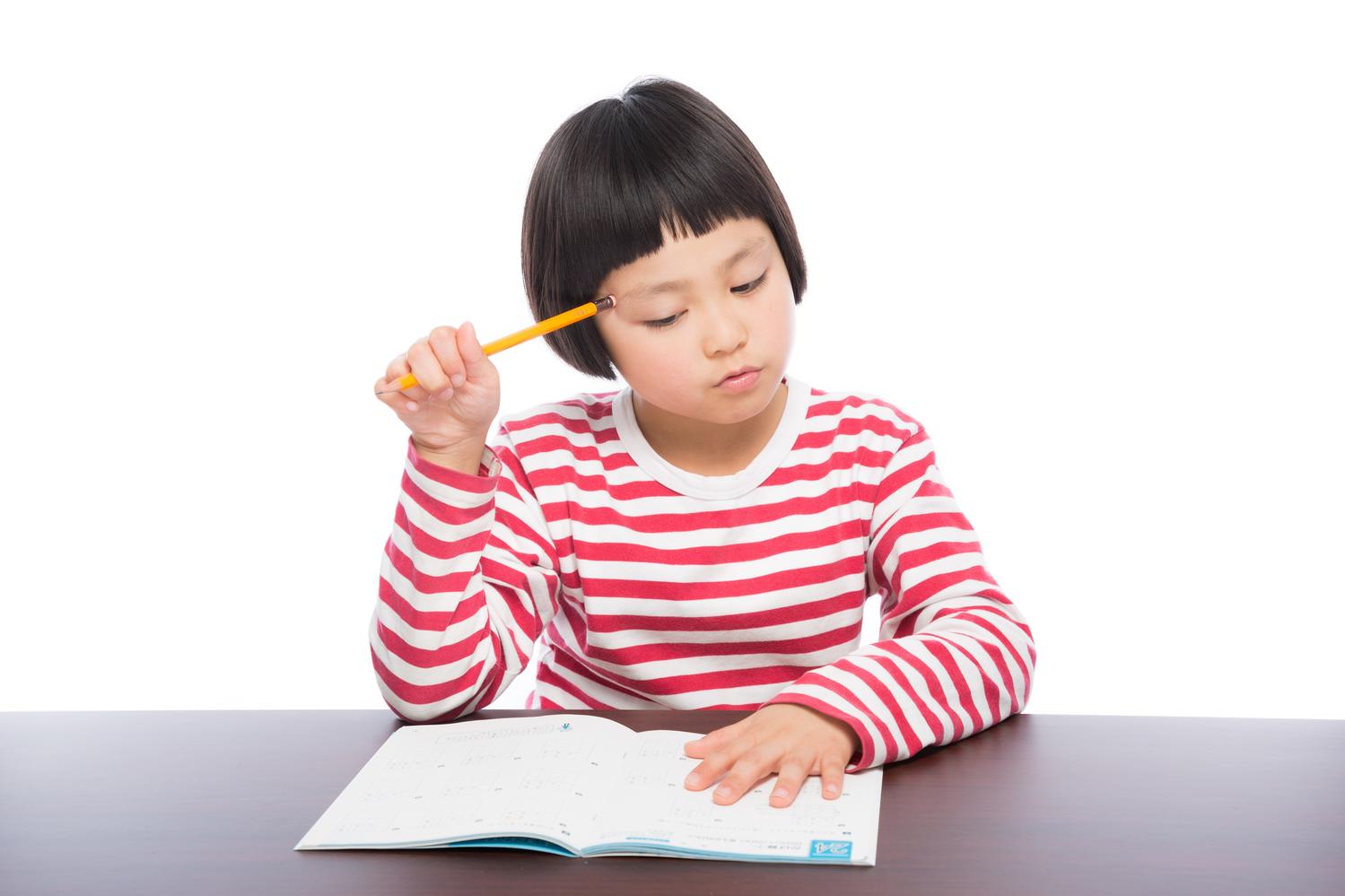
学校の教員は子どものためにと思って教育に当たっていますが、自分の意思よりも組織の方針を優先しなければなりません。
公立学校の場合は文科省の定めた学習指導要領に従って学校運営や授業を進めていかなければなりません。
学校という組織の中にいる以上、教員個々の独自のやりかたを主張しても実行することは不可能に近いです。
自分を殺すか組織の方針に妥協しながらやっていくしかないのです。
それは「自由人」になった前川さんも強調していますね。
最近は公立学校にも民間出身の校長が配置されて改革を進めているところもありますが。
なので、教員個々の問題ではなく、学校制度、文科省を頂点に据えた不自由な学校のシステムの問題です。
日本的なシステムはもうとっくに破綻しています。今後も世界のスタンダードからどんどん離されていきます。優秀な人たちは日本からどんどん離れていきます。それか自分勝手に組織と独立してやるかですね。
多くの教員は与えられた環境の中で、少しでも子どものためになったらと考えて奮闘しています。
学校からの一方的なルールを押しつけられて、それに素直に従えという方が無理があるでしょう。
子どもたちはそうやって自己主張しているんですよ。
つまり問題なのは子どもじゃなくて、学校の方です。
話が面白かったら聞くし、授業が楽しかったら夢中になって勉強しますよ。
小学校に入学したばかりの1年生が学校生活に適応できない。春になるとそうした「小1プロブレム」が問題視される。だが東京大学名誉教授の汐見稔幸氏は「教室のイスに座っていられない子どもたちの問題ではなく、そういった旧来の学びスタイルに問題があるのではないか」と問い直す。
学校や授業が楽しかったら1年生も落ち着いて勉強する
1年生を担任したときに、入学式の次の日の朝の時間にやったことです。
「いろんなあいさつをしてみよう」
学級通信は1年生が読めるように、はじめのうちは「ひらがな」で書いています。