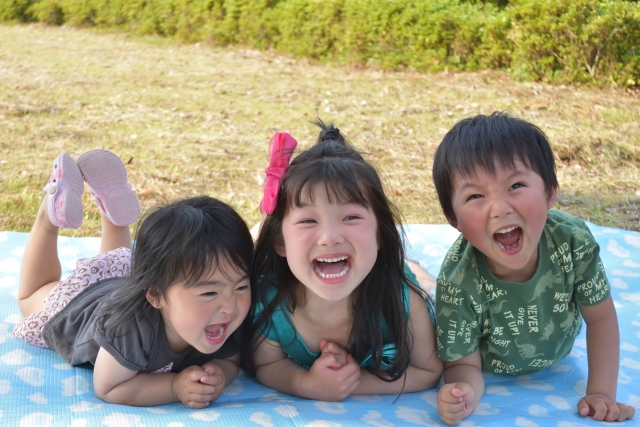
一年の終わりに近づくと、今年は「何に頑張った」とか「これができた」とか振り返りますよね。
「今年は○○にがんばったなあ。」
「がんばって○○ができるようになった。」
「できなかったことができるようになった。」
という人がある一方で
「自分はあまり頑張れなかった。」
「○○にもっと努力しないと○○できない。」
「今年はダメな年だった。」
という人もあると思います。
でも、何かができなかった、何かに頑張らなかったと考えることはありません。
だって、今ここに自分がいることが生きることを頑張っているわけだから。ここにちゃんといることに価値があるのだから。
「できたかできなかった」で見るのではなく「今ここにいること」がスゴイことだと思ったらいいです。
今ここにいるだけで100点満点なんです。生きることに十分頑張っているんです。
自分の価値は自分で決めることなのですが、多くの人は常に他者評価を気にしながら生きています。他者から見た「できたか できなかったか」「誰々と比べて優れている、劣っている」という評価によって、自己肯定感を下げてしまう人が少なくありません。親や学校からの一方的な評価によって自己肯定感を下げ、自分がダメな人間だと思い込み、自信を失っている子どもたちもいます。
もちろん、「もっとがんばろう」「○○ができるようになりたい」という向上心を持つことも大事です。
でも、できていないことは自分の中のほんの一部分です。できていること頑張っていることの方が多いんです。
どんな人もその人だけの「固有の価値」を持っています。だから自分がその価値に気づくこと、そしてそれを上手に活かせば自分らしい生き方ができます。というか今のままで十分なんです。他人から見られてどうかではなく、ありのままの自分を生かすも殺すも自分次第なんです。得意なことを仕事にすることだってできます。
「自分の存在そのものに価値がある」と気づけば、「自分も誰かの役に立っている」と感じることができます。
あなたの存在そのものに価値があります。あなたが今生きていることによって誰かの役に立っています。
みんなと同じになろうとするから悩む。
みんなと同じにしようとするから無理が生じる。
他者と比べることで優劣の評価が生まれる。
そんなことにこだわらなくてもいいんだよ。
違いはあっても優劣をつけることが間違い。
みんなが違うことが当たり前なんだから。
一人ひとりはそのままでみんなが100点満点なんだから。
そう考えたら、今ここにいるすべての人が頑張っているんです。
みんな、よく頑張って生きた一年でしたよ。
ボクも。
自分って結構頑張ってるなって思える方法
「自分はたいしたことない」「何も取り柄がない」って人があります。
そんな人は今年一年にやったことを書き出してみたらいいです。
そうしたら「自分って結構頑張ってるな」って思いますよ。
あと、自分で何がやりたいか見つからない、行く道に悩んでいる人は「やってみたいこと」を書き出してみるといいです。その中にはすぐにできることがあるはずです。
頭で考えるだけでなく、書き出してそれを見ると気づくことがあります。さらに、書き出す方法はノートにペンか鉛筆で書くのがいいです。そして、それをいつも見えるところに貼っておくといいです。
年末には「自分ありがとう」年始には「自分よろしく」です。
自分で自分をいっぱいほめてあげるといいですね。









