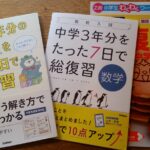「不登校」の言葉自体がネガティブイメージを与えている元にも書きましたが、言葉のイメージというのは私たちの意識や暮らしの中に知らず知らずのうちに入り込んでいます。
「不」という表現は、それを否定し排除する言葉で、上からの「支配者」によって都合のいいように操作されている、気づかないうちに大きな影響、それもマイナス、ネガティブなイメージを持たされています。
それが私たち一人ひとりの意識の中に刷り込まれていきます。
先日、小幡和輝さん @nagomiobata とお話ししたとき、「不登校」という名前が悪いんだ、ということになった。
「登校」の否定だから、後ろめたい。
だったら、「ホームスクーリング」とか、「ホーム・スクール」と名前をつけてしまえば良い。
まず、学校に行っていない君たち、部屋のどこかに、「ホームスクール中」とか「ホームスクーリングなう」とか、「ホームスクールわず」とか、紙を貼ったらいい。できるだけ明るい色で、ポップな字体で。
「Genius in homeschooling」とかいうのもいいね。
心配ない。学校に行くのは、別にオプションだから。学校に行かなくても、社会性は身につくから。
茂木健一郎ブログ「ホームスクール中」より